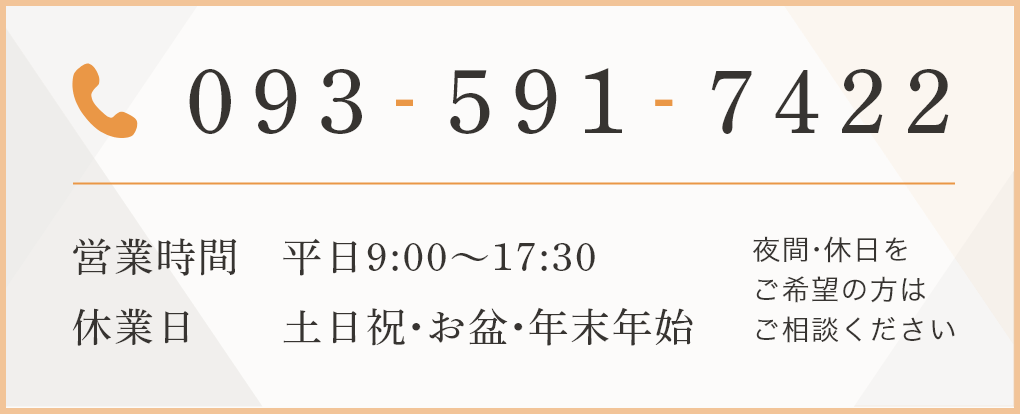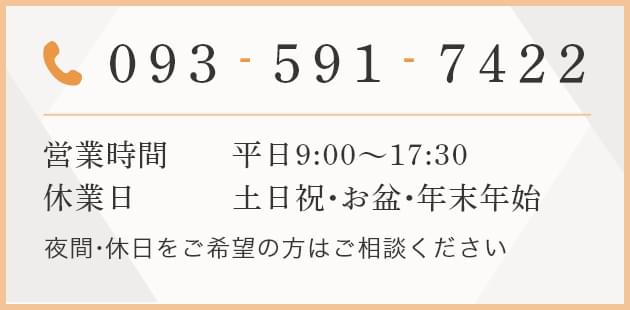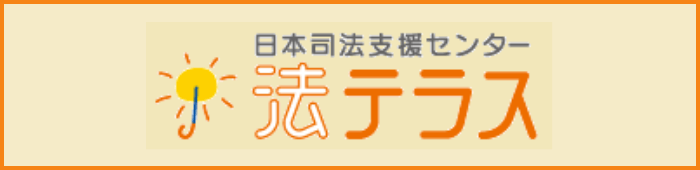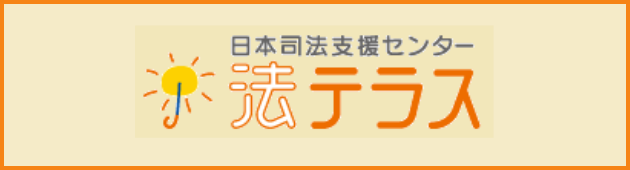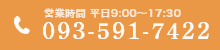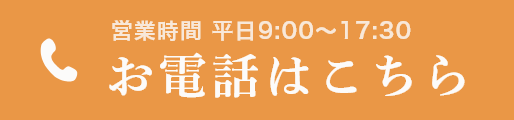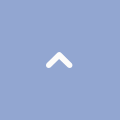相続登記の義務化①~概要
相続登記が義務化されて間もなく1年です。
改めてその概要を確認したいと思います。
1 不動産を相続、遺言で取得した者は、
そのことを知ったときから3年以内に
相続登記をしなければならない
「知ったとき」ですので、
所有者が死亡したことを「知った」
死亡した所有者から不動産を取得したこを「知った」
それぞれのときから3年です。
※ 令和6年4月1日より前に所有者が死亡していたときは
令和6年4月1日から3年以内となります。
まだ遺産分け(遺産分割)の話し合いができていなときでも
3年以内の登記の義務があります。
2 遺産分け(遺産分割)の話し合い(協議)の結果、
法律で決められた割合(法定相続分)を超えて
不動産を取得した者は、協議の日から3年以内に
登記をしなければならない
遺産分割協議とは、例えば相続権のあるABC全員で
「不動産はAが一人で取得する」などと全員の合意で決めることです。
不動産を相続したことを知って3年以内であれば
1の登記をせずに最初から協議の結果に基づく2の登記ができます。
つまり、早く協議が成立すれば、登記は1回ですみます。
逆に言えば、協議が成立するのに時間がかかれば、
1で法定相続分による相続人全員名義への登記
2で遺産分割協議の結果に基づく登記
の2回の登記をする必要があります。
これらの義務を果たさない場合、罰則があります。
3 正当な理由なく1と2の義務を果たさないときは
10万円以下の過料に処する
今までは3年以内という期限がありませんでしたので、
1の登記はせずに、協議が成立したところで
2の登記をすることがほとんどでした。
義務化により、3年以内に何らか手続きをしなくてはなりません。
しかし、相続権のある人同士が疎遠であるとか、
手続きのため戸籍を調べるて、全く知らない相続権のある人の存在を知った
という場合など、簡単に協議ができないこともあり得ます。
その場合でも相続人全員名義の相続登記を
しなければならないとなると負担は小さくありません。
そんなときに、全員でなくてもできる手続きが創設されました。
それが「相続人申告登記」です。
これについては次回、ご説明します。